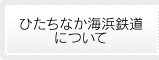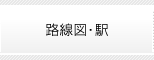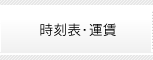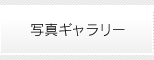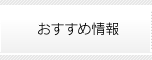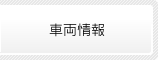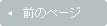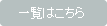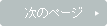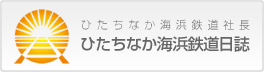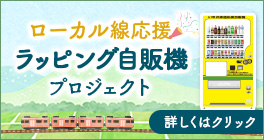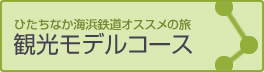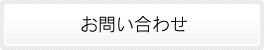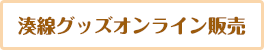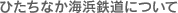海浜鉄道日誌
偕楽園にぎわい 連携できれば
18日、茨城県立歴史館で開催された「特別展那珂湊反射炉 みどころ解説1」に参加。那珂湊の象徴ともいえる反射炉について講義を受けました。奥が深いです。ためになります。もっともっと知りたくなったりして。
そのお話はあらためて場を設けるとして、行き帰りのアクセスと梅まつりの始まった偕楽園の様子が勉強になりました。
往路は、水戸駅から茨城交通の路線バスで歴史館偕楽園入口へ。下調べはしたのですがバス乗り場ではちょっと戸惑います。やっぱり鉄道はいいな。
茨城交通のバスは時代の先端を走っていて、なんとクレジットカードのタッチ決済に対応。支払方法が分からないので運転手さんにお尋ね。「乗車口のセンサーにタッチして、降りるときに運賃箱のセンサーにタッチ。整理券は不要。」とのこと。なるほど便利です。Suicaを持っていなくても、全世界の人たちに対応できる優れものです。しかも運賃は10%割引で216円。そのうちに湊線にも…。
復路は、少し歩いて偕楽園駅から常磐線に。が、歴史館のどこを見ても駅へのアクセス案内はなし。まあ、そういう利用者がいないんでしょうけれど。
道端の掲示板や偕楽園入口の案内のお姉さんんを頼りに、どうにか駅へ。徒歩で10分弱でしょうか。駅に着いたのが15時34分。わずか2分前に列車が。次は55分です。ちゃんとアクセスがどこかに明示されていたら迷わずに前の列車に間に合った気が。でも「臨時駅を大々的に書いて誤解を招く弊害も大きそうだからしょうがないか。」などと思いながら乗車。勝田まではIC利用で199円。運賃は安いです。
歴史館まで徒歩0分で本数もそこそこのバス。お値段は安いけれど、臨時設置でしかも水戸方面しか使えない鉄道。
これだけ差があると、やはりバスに軍配が上がるようです。
ちなみに暖かい気候のせいもあり、偕楽園は人でいっぱい。正直、湊線からほど近いこちらにこんなにたくさんの人が来ていることに”今さらながら”驚きました。百聞は一見に如かず。やっぱり狭い視野でものを見ているのは良くないようです。
この人たちと那珂湊をもっと結びつけると、ひたちなか市の経済にプラスになりそう。会社に帰って、ちょっと作戦を練りましょうか。
偕楽園駅の構造と鉄道の定時制を勘案して、東京方面からはひたちで偕楽園→常磐線で勝田→湊線で那珂湊おさかな市場→帰りは湊線&ひたちで時間どおりお家へ。こういうのをもっともっとアピールしないといけませんね。